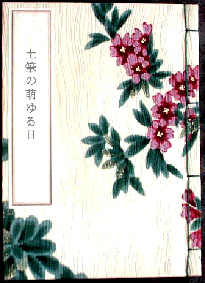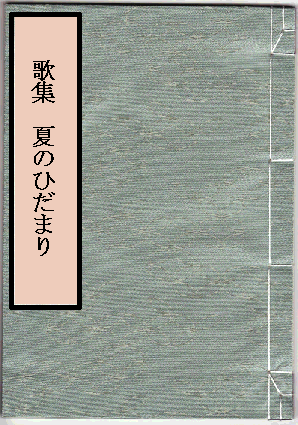| 和本教室 | 和本を作る 四つ目とじの糸とじ本を作ります | |||
|
四つ目とじ和本作り 体験番号75
|
||||
|
||||
|
和本の代表格「四つ目とじ本」を作ります。和紙を折って束ねた中身の端(背側)に四カ所穴を開けて、糸とじするところから四つ目とじと呼ばれます。日本では奈良時代から長く用いられてもっとも一般的な和本です。
特徴は柔らかくて強い、にありますので、和とじ館では柔らかな薄和紙を用いて本体を作り、表紙には緞子や金襴緞子の伝統文様の美術布で作ります。本格的なきれいな和本ができあがります。 上写真のような高貴とじ本も出来ますので、ご希望の方は申しつけてください。記念帳などに相応しい綴じ方です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 材料:本文(中身)には土佐和紙の薄様紙か、経本用和紙を使用。 表紙:古典文様緞子、金襴緞子、染め布を使用。希望者には手描き友禅(別途料金)もあります。 講師:輿石恵美子(こしいしえみこ)和とじ職人 時間:午前コース:10:00〜12:30 昼コース :1:30〜4:00 費用:4500円(税込) ○ご予約ください。 (補)別料金となりますが、正絹の金襴緞子や手漉き和紙(吉野楮紙・倉敷雁皮紙越前手漉き紙)などのご利用もできます。前もってご一報ください。(+1000円〜3000円ほどです。) 連絡先:077−575−2912(10:00〜17:00月曜から土曜日)
京都和とじ館 電話077−575−2912 fax077-521-2521
お尋ねやメールでの申込みは→こちらから
京都和とじ館への道→和とじ館への道へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ KBS近畿放送ラジオ番組の取材を受ける輿石恵美子
私はスケッチが好きで、以前からスケッチしたものを、見まねで糸でとじ冊子にして遊んでおりましたが、大阪で世儀義夫先生に和とじのご指導を受け、和本の楽しみに接することができました。夫の輿石が編集・出版をやっておりますので、本格的に編集した本を和本にしたててみようと、1999年私の絵と輿石の文で「おきなわ民話の旅」という本を和紙に印刷し、沖縄の伝統布を表紙に作ってみました。意外にも「アエラ」誌上に取り上げていただくなど、多くの方から多々反響をいただきました。それ以降和本の魅力に取りつかれてしまいました。なによりも簡単に出来るのがすばらしいです。それに自由に絵を入れたり、表紙に色んな素材を用いたりでき、一冊一冊作るのが楽しくなります。また「こんなものが出来た」と意外な本をお持ちくださる方などいて、本当に楽しく作らせていただいてます。ご指導など大げさですが、私の出来ることを皆様にお教えし、より面白く楽しい和本ができればと思っております。どうぞ気楽にお遊びにおでかけください。 2004.11.5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|
||||
|
|